町長ふれあいトークの開催記録(平成26年8月21日開催分)
町長ふれあいトーク 平成26年8月21日開催分
- とき 平成26年8月21日(木曜日)9時30分~11時
- ところ 筑紫集落センター
- 参加者 筑紫永楽会(28人)、町長、総務部長、福祉部長、環境防災課長
今回の主な内容
- 東日本大震災の教訓から考える
- 日本の人口推移から考える
- 東員町の現状
- 平成26年度の3つの方針
町長トーク
東日本大震災の教訓から考える
私たちの生活は隅々までお金に支配されています。しかし東日本大震災が起こった後は、お金がいくらあっても電気も食べ物も水も買えない、そんな日が何日も続きました。いざとなったらお金には何の価値もないんです。本当にお金がすべてでいいのでしょうか。
私たちの生活は多かれ少なかれ中央集権という形でコントロールされています。行政に税金を納め要望を出すことは当然の権利です。しかし災害が起きた時に行政がすぐに駆けつけて何かをしてくれることはまずないでしょう。すぐに行政が何かをすることは絶対に無理です。ですから自助・共助を大切にしていただきたいのです。自助とは自分で自分のいのちを助けること。東日本大震災なら津波が来るから早く逃げろということ。次に共助、お隣の方も一緒に逃げましょう。そして最後に公助、行政の助けがくる。やはり公助には時間がかかります。まずは、自分で自分の命を守ることが大切です。町民の皆さんは2万6千人、役場の職員は200人。1人当たり100人以上見なければならないわけですがすぐにそれができるかというとそれはできない。ですから自分たちのことは自分たちでできるようにしていただくことが一番いいのではないかと思っています。
日本の人口推移から考える・東員町の現状
日本の人口は、終戦時は7~8千万人でしたが1955年には9千万人、高度成長期にも人口は増え続け、2008年が日本の人口のピークでした。そして現在は人口が減ってきています。1955年の高齢化率は5%でしたが、今は20%を超えています。東員町の高齢化率は4月で24%。毎年2%ずつくらい増えているので来年には26%になるでしょう。
人口が増え続けているとき、行政は何でも任せてくれという体制でした。昔、千葉県の松戸市に「すぐやる課」という課がありました。住民の方からの要望があればすぐになんでもやるという課でした。当時は全国であちこちにこのような課ができました。何でもかんでも要望があればすぐにやるというのが当時の行政でした。しかし今は違います。当時に比べて市町村でやることが格段に増えました。特に福祉関係はほとんど市町村でやることになってきました。ところが職員の数は国から定数を決められていて増やすことができません。今役場は非常に忙しい状況です。右肩上がりのときは仕事も少なく職員の数も多かったので何でもできる状況でしたが今はできません。しかし役所の制度自体は人口が増え続けていた当時のままです。ですから制度自体を人口減少に向けたものに変えていかなければならない。これがこれからの私たちの作業だと思います。そうしなければこの社会はもたないでしょう。
日本の借金は1千兆円を超えています。また人口が減ってきているのに日本は道路を作り続けています。2050年ごろには日本の人口は9千万人くらいになり車の台数も減るはずなのにこんなに道路を作っていいのか疑問が残ります。これからは人口減少を見越した制度に変え、借金を減らし、将来に良い町を残していけるような東員町にしなければならないでしょう。
日本は成熟社会に入っています。地域の特色なんてない時代がありましたが、それでは満足できない時代になりました。自分たちの意思に沿った町づくりが必要になってきました。行政にすべて任せるのではなく、皆さんには皆さんの生きがいづくりや自分たちの生活ができるような町づくりをしていただければと思います。これから政策課の者が順次皆さんと町づくりについて話し合いを進めていきます。一律の町づくりをするのではなく皆さんの意思に沿ったような地域づくりをすることでいざ何かあった時には自分たちの地域・いのちを守れるような地域をつくることにつながるのではないかと思っています。
平成26年度の3つの方針
今年の東員町の政策は大きく分けて3つあります。1つ目は「地域力を創る」、2つ目は「いのちを守る」、3つ目は「健やかに育ち育てる」です。
1つ目は「地域力を創る」。皆さんの生活、思考に合った地域創りをしていきたいと思っています。現在東員町には1つの課題が出てきています。東員町はネオポリス、神田・稲部地区、そして三和地区の3つの地区に分けることができます。ネオポリス地区は、ピーク時は在来地区の1.5倍の人口がありましたが今では高齢化、人口減少が進んでいます。一方神田・稲部地区は人口が増加しています。神田小学校は子どもの数が増えたため仮設校舎を建設しました。稲部の保育園は去年園舎を3教室分増やし今年は学童保育の施設を立て直し大きくします。しかし三和地区の方は住宅開発ができない地区であるため子どもの数も減少気味です。このため東員町の人口バランスは非常にいびつになってきています。子どもの数が増え小学校・保育園を増築しなければならない地区がある一方、三和地区は空いています。三和地区に住宅を建てられるようにするには県の許可が必要なので、現在県と協議をしています。
2つ目は「いのちを守る」です。人口バランスを整えて地域を創るのは、皆さんの命を守るということが大前提だからです。何かあった時に近所同士助け合いながら守っていくことが大切だと思います。以前八幡新田地区の防災訓練に参加することがありました。八幡新田では全戸に黄色い布を配布しており、何かあった時に全員が避難した家はその黄色い布を玄関口に出します。こうすると黄色い布が出ていない家にだけ救助に入ればよく、また地図に井戸のある場所が書いてあり、水がなくなったときどこで手に入るか地図を見れば分かるようになっています。またどこに要援護者がいるかも書いてあり誰が助けるかも書かれています。非常にうまくできたシステムです。いざというときにはなかなか実践できないかもしれませんがきちんと用意しておいたほうがいいと感じました。みんなの力で自分たちの近隣の人々を守る、こういった地域を創るには普段から地域のつながりを強くしておくことが大切なのではないかと思います。そのために行政も地域の皆さんと話をさせていただき、お伺いした要望や話を大事な施策にしていきたいと思います。
最後は「健やかに育ち育てる」です。住みやすく財政も安定している東員町をこのまま子どもたちに残していくことは務めだと思っています。また、その子どもたちをいかに健全に育てるかが私たちの役目だと思っています。すべての子どもには健全に育っていく権利があります。しかし虐待やDVなどのために子どもたちが弱っています。自殺している子ども、殺される子どももいます。こんなことはあってはいけない。そこで東員町では子どもが健全に育っていけるように「子どもの権利条例」を作っていこうとしています。子どものことですから子どもの意見も取り入れるため子ども委員会と大人委員会に分けて進めています。子どもたちがはつらつとしながら取り組んでいます。始めてから1年半たつのですが委員会の子どもたちはものすごく成長しています。子どもたちにも言っているのですが、自分の権利を主張するためには相手の権利も認めることが大切で、子どもたちはそこまできちっとわかっています。そんな子どもたちが東員町で育っています。皆さんもお孫さんが健全に育っている様子を見ていただいていると思います。
最後に、東員町の特色は何だと思いますか。町長をさせていただいて3年半経ちますが驚いたのは文化度の高さです。皆さんが自主的にいろんなことに取り組んでいます。定年後陶芸サークルに入りプロ並みの腕前になった方がいらっしゃるのですが、その方は今でも東員町文化祭になると必ずその陶芸サークルに作品を出してきます。つまりそこが原点なんです。日本語で歌う第九も今年で26年目です。鎌倉市の第九では参加者およそ300人、東員町は100人ほどですが東員町の第九は日本で一番古く歴史があります。なかにし礼さんの作詞で12月23日に行われます。今年もぜひ皆さんにご参加いただきたいと思います。こども歌舞伎は来年20周年、飛龍東員太鼓は去年25周年、朗読ひばりの会が今年26年目、そして北勢線は100周年。この100周年を記念してミュージカルを行います。去年は上げ馬をテーマにしたミュージカルで大好評でした。今年は2日間行います。11月22、23日です。地元の方が20人弱出演しており今年も素晴らしいものができると思います。
東員町は非常に文化度が高く自分たちで自分たちの生活をつくっている。これからも自分のことは自分でしていただく、そして行政はそれをお手伝いするという形にしていきたいと思います。それが将来まで子どもたちに良い東員町を託していくことにつながると思いますのでよろしくお願いいたします。
質疑
参加者
配布される印刷物に英語で書かれていると意味が分かりません。使うときは括弧書きで意味を書いてほしい。
町長
それは非常に不親切なので改めさせていただきたいと思います。
参加者
介護予防教室のとき職員がお年寄りの前を通るときに何も言わなかったり座布団を足で片付けたりしていて腹が立ちました。
町長
基本的な礼儀に問題があり直すように伝えます。
参加者
この間の大雨で特別警報が出ましたが、この筑紫の集落センターまで避難するなら家にいても変わりません。神田小学校まで避難するのは遠くて高齢者にはかえって危険。例えば避難所をお寺にするなどもっと近くにしてもらうことはできませんか。
参加者
雨が多いと、この筑紫の集落センターの前は川みたいになる。避難するのはかえって危険。
総務部長
特別警報のときは一時間おきに職員が巡回をしました。この間は避難準備情報を出しましたが、大雨のときに避難するのは二次災害が起きてかえって危険です。今後皆さんの意見を聞きながら避難経路を考えていきたいと思います。
町長
基本的には集落内で一番集まりやすいところが一時避難所になっています。筑紫の場合、集落センターが一時避難所として危険だと判断されるなら、自治会長さんを中心に皆さんで話し合っていただき別の場所を指定していただいたほうがいいと思います。避難所である小学校は災害が発生してすぐに移動するのではなくどうしようもなくなったときに避難してもらうほうがいいでしょう。地域のことは地域の皆さんが一番よく知っています。まずは皆さんで話し合っていただいて指定していただくのが一番良いと思います。
参加者
現在、保健福祉センターで介護予防教室などがあるときには個人の車にみんなで乗り合わせて行っています。話を聞きに行くため町からお迎えのマイクロバスを出してもらえませんか。
生活福祉部長
10月からオレンジバスの路線が変わり今までとは違って筑紫の方にもご利用いただけるルートになります。そちらも利用していただき、先ほどの町長の話にもあったようにこの東員町をより良い形で次の世代に託していけるようご協力をお願いしたいと思います。
参加者
昔はオレンジバスが弁天橋の方まで来ていましたがもう来てくれることはないのでしょうか。
政策課長補佐
今のところそのルートの設定はありません。オレンジバスは細い道が通れないこととバス3台でルート編成を行っていることが主な理由です。しかし皆さんからのご要望が多ければ考えさせていただきたいと思っています。
町長
もちろんオレンジバスのルートは今回の変更で固定というわけではありません。皆さんの声を聴いて順次変えていきたいと思います。
参加者
バスが来るからという理由で講座の途中で帰ってしまう方がいます。講座の終了時間とバスの時間をうまく組み合わせてもらえませんか。
町長
講座の時間をうまく調整するようにします。
参加者
オレンジバスが時間通り来ない。バス停で待っていても行ってしまうこともあります。
政策課長補佐
待っていても行ってしまうのは非常によくないことですのでバスの運転手に注意します。オレンジバスは交通事情の影響で遅れることもありますので遅延についてはご了承ください。
参加者
いくつか講座がありますがこちらまで来てお話してもらうことはできますか。
政策課主幹
役場で出前講座を行っているので申し込んでいただければ役場の職員が出張させていただくこともできます。
参加者
曜日や時間が合わないと来ていただけないのではないですか。こちらは何曜日に行うか決まっているので時間を合わせてきてもらえませんか。
政策課主幹
平日に行うものには対応させていただいているので申し込んでいただければ出張いたします。
終了
(補足)記録は要約してあります



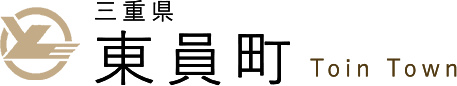

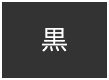
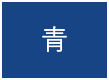
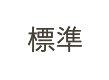
更新日:2024年03月29日