町長ふれあいトークの開催記録(令和元年7月6日開催分)
町長ふれあいトーク 令和元年7月6日開催分
- とき 令和元年7月6日(土曜日)14時~16時
- ところ 保健福祉センター
- 参加者 東員町をより良くする会ほか(140人)、町長、政策課長
今回の主な内容
第1部
- 新しいまちづくりへの挑戦「町長3期目の抱負と長期展望」
- 農業振興策の現状と展望「稼げる農業に繋げるには」
第2部
- 北勢線の自立と存続の在り方
- 関心の高い政策課題
第1部 新しいまちづくりへの挑戦・農業振興策の現状と展望
町長
お題をいくつかいただいていますが、全てがつながっており、我々の目指すところは1つです。分けて質問いただいていますが、一連で話をさせていただきます。我々がやろうとしていることは、東員町のためになることであって、さらに日本のためにもならなければならないと思っています。日本は大きな借金国です。地方創生といっていますが、それが実現しているかというとそうではありません。東員町がやろうとしていることは、どこでもできるといったモデルを作りたいと思っていますし、それが日本のためになると考えていますので、そういう観点でお話をさせていただきます。
東員町は今、非常に厳しい財政状況にあります。これは日本中どこでも同じ状況です。これからは国を頼りにするのではなく、東員町が自立するのだという、自分たちで自分たちの生活を守っていくのだと、そのために稼がねばならないと思っています。今財政力指数からみると3割くらいは国に頼っていますので、それを2割、1割と小さくしていかねばならない。これが、東員町が自立していくことだと思っています。
皆さんの中には企業誘致をして企業からの税金で潤わせればいいという方もいると思いますが、東員町は東西4キロ南北6キロの小さな町です。工場を誘致するような場所はほとんどなくなってきています。東員病院横のハイブリットパークに5,000坪の区画が4区画あり、3区画は埋まりました。1区画残っていますが、これもそのうち埋まると思っています。それならば農地をつぶせばと言われるかもしれませんが、農水省の規制があり難しい。東員町は面積の3分の1が農地です。では、700ヘクタールの農地が一体どれくらい稼いでいるのかというと、農業収入は3億7,000万円ほどしかない。1反あたり5万円ほどで、ほとんど米の値段です。これでは農業者が食べていけない。そこで今、農地を集約するとか、認定農業者を増やして大規模農業をしてもらうなど、色々取り組んでいますがこれではいけない。農業で食べていけるようにするためには付加価値をあげるしかないと思っています。農地は規制があり農地として利用するしかないわけです。行政が農業に手を出すことはどこでもあまりやったことがないですが、東員町としては農地を活かし、稼ぐことをしないと東員町の将来はないだろうと5年ほど前から取り組んでいます。
今、大豆に着目をして稼いでいこうとしています。四日市市にあるミナミ産業という企業に協力いただき、大豆を育て加工して製品にし、付加価値をあげるといった6次産業化で農業者の収入を増やすことを第一弾として取り組んでいます。大豆からおからがでない工程で豆腐を作ると、捨ててしまうおからが出ないので、量は倍になります。非常に濃くて美味しい豆乳ができ、少々高くても売れます。油揚げもとても美味しいものができます。役場南にあるカフェレスト「くろがねもーち」で売っていますので、ぜひ食べていただきたい。少し高いですがよく売れています。
大豆は全国的に9割が「フクユタカ」という品種を生産していますが、「ななほまれ」という機能性成分の高い大豆に変えていこうとしています。中性脂肪を下げる機能性たんぱく質を多く含む大豆です。計画では、去年一部「ななほまれ」を撒き、今年は10ヘクタール撒きます。今年とれた大豆で来年は20ヘクタールに、再来年は40ヘクタールにしようと思っています。この大豆でできた製品は年末から来年くらいに生産できると思っていますが、非常に付加価値が高いので高く売れると予測しています。来年には四日市のこの企業と町内農業者とで、町内で法人を立ち上げ、工場、販売所、食事ができる所も作っていきたいという計画を立てています。東員町でとれたものが東員町で加工、販売ができ、町内でお金が回る仕組みができます。東員町のブランドができて、売り出すことができると思っています。
今はまだ「フクユタカ」で製品を作っていますが、これからは、「ななほまれ」で豆乳や豆腐などの大豆加工品を作っていきます。今でも、大豆、米粉を使ったドーナツやシフォンケーキ、クッキーなどのお菓子はできています。それを拡大して、また別のものにもチャレンジをしていきたい。例えば豆乳マヨネーズを開発するなど、これも美味しければ体にもいいので、爆発的に売れると思います。このような展開をしていき、東員町の物を外に向かって販売していきたいと思っています。しかし、まずは町内の皆さんに食べていただければ大変ありがたいと思っています。町内だけでなく日本中に東員町ブランドのオンリーワンを作っていきたい。今は何もないですが、「東員町といえばこれだ」というものを作っていきたいと思っています。そして農業者が稼げるようになれば、農業に参入する若者が現れると思います。
これからは、1次産業は非常に大事な産業になると思っています。世界でみれば食糧難なのですが、日本は6割を輸入しています。世界情勢では人口が増えており、人が増えれば食料がいります。日本に食料が入ってくるのが難しい時代が必ず来ます。それに向けて農業に注目し、農業者を増やしていきたい。700ヘクタールの農地を有効活用できれば、東員町の人口は自給自足できると思います。そのためには農業で稼げることが必要だと思っています。
第1部質疑応答
参加者1
おからの出ない豆腐を長野県で作っていて、技術としてすでにあると思いますが、「ななほまれ」を使うのがオンリーワンなのですが。
町長
以前、ミナミ産業が長野県と組んでいましたので、長野県の技術も関係していると思います。微粉末に粉砕する製法は、ミナミ産業の特許になっているのでどこもまねできないもので、今は、東員町と組んで進めています。「ななほまれ」は長野県が元ですが、凝固性が弱く、普通の製法では豆腐が作れないので、東員町でそれをやろうと進めています。ミナミ産業と町内の2法人と東員町と三重大学が連携して産官学で事業を進めています。「ななほまれ」は東員町にしか種がなくなってきていますので、そこも含めて東員町オンリーワンを考えています。
参加者2
以前、アボカドの売り込みの戦略をするときに「森のバター」という言葉を使ったら、太るようなイメージで失敗したという話を聞いたことがあります。今の話は非常に興味深いですが、健康にいいとか中性脂肪とか、美味しいというのは、一般的に受けにくいと思います。すべてはイメージ戦略と思いますが、そこはどうなりますか。
町長
まだそこまでいっていませんが、実は教育長は糖尿病の気があって、HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)の基準の6.2に対して、10を超えていました。そこで私がこの豆乳をすすめました。なぜなら、この豆乳は、大豆を平均が0.2ミクロンの微粒子の粉末にし、水に溶かして豆乳に加工していますので吸収がいい。2ヵ月飲み続けたら8くらいに下がりました。効果があったかもしれないと飲み続けて今6くらいに落ち着いているそうです。できるだけ食事の前に飲むと吸収がよく、飲んだ後に食事をとると、糖の吸収を抑えてくれるらしいです。実際にこういった結果もありますので、健康にいいと思っています。イメージ戦略はこれからの話で、色々考えていかねばならないと思っています。
参加者3
具体性に欠けているような気がします。こういったことに取り組んでいく内容はいいのですが、今の段階で物になる可能性は低いような気がします。もう少し煮詰まってから話をされたらと思います。
参加者4
大豆や揚げなどの商品はどこで作っているのでしょうか。
町長
大豆は農地700ヘクタールのうち150ヘクタールの面積を東員町内で作っています。これは町が関わっていないものも含めてです。町としてはその中で一部、「ななほまれ」を作りました。「フクユタカ」も作っています。町が関わっているのは、その中の何分の一かです。大豆を加工しているのは四日市市のミナミ産業という会社の工場で作っています。その工場を来年東員町に建設して、東員町でとれたものを町内で加工できるようにしていきたいと思っています。具体性に欠けるとの話がありましたが、農業というのは時間がかかると思います。これを地道にやっていかねば成果がでない。成果ができて、農業者が自分たちでできるようになるまで、行政が入っていた方が有利な場合が多いです。実際、助成金ももらっていますので、今は産学官で連携して取り組んでいます。
第2部 北勢線の自立と存続の在り方・関心の高い政策課題
町長
まず、北勢線の在り方ですが、平成15年に近鉄から三岐鉄道に移管されました。個人的な話ですが、私が県議会議員の時に、北勢線を鉄道で残すことは大反対しました。赤字が続くこと、運賃が上がること、乗車人員が減ることを訴えました。今その通りになっています。私が8年前この職について、立場が逆になりました。町民の皆さんも含めて、桑名市、いなべ市、東員町も含めて、皆で残すという住民の皆さんの意思で残ったわけです。結論からいうと、三岐鉄道の自立は絶対にありえないと思っています。このまま存続するならば、桑名市、いなべ市、東員町がいくらかの補助をしていかねば存続はしないと思っています。私は三岐鉄道に、もっと自主努力をしてくれといつも言っていますが、3億くらいの年間赤字がでており、ほとんど減っていません。平成15年の段階で10年たったら、自主運行をという約束でしたがそれは無理でした。三岐鉄道も行政や住民の皆さんの努力によって、少しずつ乗車人員は増えていますが、赤字解消までにはいかないのが現状です。数字については政策課長からお話させていただきます。
政策課長
平成15年に近鉄から三岐鉄道に移管され、駅の整備や線路の修復や高速化など、10年間で国・県・市町が86億円を投入しています。そのうちの18億円、約2割が東員町からの支出となっています。それが10年間の費用で、11年以降は安全運行をするために、車両の修理などのハード面の整備を行うのに、1年間で約4,800万円を東員町が支出しています。利用状況と赤字額ですが、最初の10年間は投入した費用が高いため、赤字も高くなっていますが、10年後以降は約3億円程度の赤字が続いています。そのうちの2割の4,800万円を町が負担しています。乗車人員については、最初少し減りましたが、相対的には少しずつ増えている状況です。分析をしますと、少子化に伴い、通学定期が平成14年と29年を比べると2割くらい減っています。通勤定期は2割ほど増えています。定期以外は1.5倍となっています。乗車人員は少しずつ増えていますが、黒字まではいかず、安全を担保するためには、行政からの支出が必要であるのが現状です。三岐鉄道、桑名市、いなべ市、東員町で、色々なイベント等で啓発事業に取り組んでいるのが、功を奏しているかとは思いますが、通勤定期がまだまだ伸ばせるのではと検討している状況です。北勢線は公共交通事業ですので、誰もが移動できること、車に乗れない世代、高齢の方等の移動手段としてできるだけ確保していくべきと取り組んでいます。そのために、いなべ市、桑名市、東員町、三岐鉄道で北勢線事業運営協議会を設けて、様々なイベント事業などを検討して進めているところです。
町長
関心の高い政策課題ですが、まず、東員第一中学校の老朽化について、一番古い校舎が築50数年経過しています。当時鉄筋コンクリートの耐久年数は60年と言われました。耐震はしていますが、早急に手を打っていかねばならない。我々は、東員第一中学校をどうするかを、その場で建て直すかを含め、協議をしてきました。この学校は、東員町と桑名市の一部事務組合で建てられたので、桑名市西部の生徒も対象となり、東員町の東の端にあります。長深、大木、南大社からの通学は非常に遠い道のりです。この通学距離の是正も含めて考えていくべきという意見もあり、総合的に考えた結果、真ん中にもってくるべきと結論を出しました。昨年、駅前開発計画で中学校も入れようとしましたが、規制や時間の制約で断念せざるを得なくなりました。その時に、中学校をどうするかとアンケートをとりましたが、真ん中にという意見が多く、8割近い方がそう答えていましたので、県や国の関係機関と話を進めてきました。ようやく今年の始めに、役場の隣接地に移転することが可能という判断をいただきました。早速進めていこうと、教育委員会職員が地権者に挨拶に伺い、折衝させていただいています。役場北側に、中学校ができれば、ひばりホールを供用できます。体育館は中学校に作りますが、大きな大会の場合、総合体育館が使えます。武道館もあり、役場周辺施設が供用できるメリットと、今まで遠かった通学距離が短くなるメリットもあります。そのためには、山田、北大社の皆さんの協力をいただかねばなりませんので、お願いに伺っています。我々の今の目標、計画では令和5年に新しい中学校を開校したいのですが、地権者の同意が必要ですのであくまで目標として、進めていきたいと思っています。新しい学校は、小中学校、幼稚園保育園を含めて、中心となる学校にしていきたいと思っています。
では、笹尾・城山地区はどうなるのかですが、東員第二中学校があります。子どもの数は減っていますが、廃校するほどの減り様ではないです。笹尾西・東小学校では、減少の底を打ってきた感じがありますので、今のところ現状でと思っています。ただし検討の最中で、校舎も老朽化しますし、児童数が減る状況であれば、一つの案ですが、隣接する東員第二中学校と笹尾東小学校を、新しいタイプの小中一貫校として建設するという案も出ています。ただ、中学校を一つにするのは難しいと判断しています。東員町は自治体としては珍しいですが、子どもの数が20年先と今の数字がほぼ同じくらいと推計していますので、今すぐ学校の改編は考えられないと判断しています。東員町は子育て、教育に先進的に取り組んでいると評価いただいていますので、継続していきたいと思います。
また、皆さんが活躍、活動していただいており、東員町は文化度が高い町と言われています。これは、先人の皆さんが、物質ではなく心の豊かさを求められて取り組んでいただいた賜物と思っていますので、文化の町として皆さんが心豊かに生活できるようなまちづくりをしていきたいと思っていますので、ご理解ご協力をお願いします。
全体の質疑応答
参加者5
稼げる農業ということですがJAと協力しているのですか。現在の農業従事者の中で賛成しているのはどれくらいいるのですか。
町長
今、大豆について一緒に取り組んでいるのは2社あります。来年くらいには4社くらいに増やしていかねばならないと思っています。最終的には80ヘクタールほどの規模になれば参入される方に参入していただけるようにならねばいけないと思っています。まだ途中の段階ですので、当面の目標は、3億7,000万円の生産額を10億にしていきたいと思っています。
参加者6
東員第一中学移転後の跡地の利用計画はありますか。
町長
計画は色々と考えています。というのも、色々なところから問い合わせをいただいています。施設を建てるとか、具体的に話ができる段階ではないですが、最適なものを考えていきたいと思っています。他には、すべてを住宅にするということも考えられますが、165区画くらいの住宅ができた場合、神田小学校が大変なことになりますので、そこまで考えねばならない。今問い合わせいただいている所でなんとかできないかとは考えていますが、ただ一部は住宅開発になるのではと思っています。
参加者7
ふれあいトークを年2、3回開催されてはどうでしょうか。
町長
制度としてふれあいトークがあります。20人以上の方が集まり場所を確保していただき、私が出向く制度です。要望される時期に伺えるかはわかりませんが、こういった制度がありますので、ご利用いただければ思います。ただし、1つの団体で年1回となっていますので、今年度は今回と別の団体であれば、こういった機会を設けることができます。
参加者8
町長の所信が見えなかったのが残念です。大豆ですが、色々な意味で町長は失敗をしていますが、今回も絵に描いた餅ではないかと危惧しています。北勢線については、今の組織を完全に変えないといけないと思います。組織の変更について町長はどう考えていますか。
町長
確かに色々失敗をしているのはその通りです。ただ、失敗が無ければ成功はない。私は職員には「失敗はいい。ただ、倒れるなら前に倒れなさい」と話をしています。必ず成功するものにチャレンジはないと思っています。私のモットーは、財政的に厳しいのでできるだけ税金を使わないようにしています。駅前は断念しましたが、使ったお金は東京に陳情したお金や調査をしたお金で、ほとんど使っていません。チャレンジをしていかない限り東員町の将来はないと思っています。これからも、失敗するかもしれませんがチャレンジし、身を結ぶような最大限の努力をします。農業については、今のところ順調にいっています。
北勢線の組織とはどういうことですか。
参加者8
北勢線の協議会がありますが、各自治体から集まっているこの組織が充実しているのかというと、そうではないと思っています。住民主体の組織にするとか、根本的に変えないと今まで通りと危惧しています。例えば、分担金がありますが、20年間ずっと変わっていないです。そうではなく色々なやり方があるのではないでしょうか。
町長
北勢線運営協議会の組織改編は難しいと思っています。なぜなら、東員町だけで決まる話ではなく、桑名市、いなべ市、東員町が入っています。北勢線の存続は住民の皆さんが決めたことで、議会、行政も含めて、皆さんで決めたことです。それを粛々と行っています。首長の中には三岐鉄道が必要なものはすべて出すという方もいます。東員町だけの意見が通るかというと難しい。運営協議会を変えることは、現実的に可能かというと、非常に難しいと言わざるを得ないと思っています。
備考
(補足)記録は要約してあります



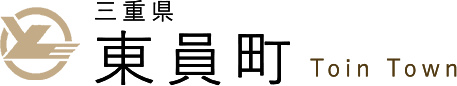

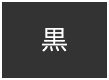
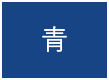
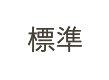
更新日:2024年03月29日