町長ふれあいトーク 令和元年9月11日開催分
町長ふれあいトーク 令和元年9月11日開催分
- とき 令和1年9月11日(水曜日) 9時30分~10時30分
- ところ ふれあいセンター
- 参加者 東員町シニアクラブ連合会(35人)、町長、長寿福祉課長
今回の主な内容
- 主催者挨拶
- 地域の中での今後のシニアクラブの役割
- 主催者御礼
地域の中での今後のシニアクラブの役割
町長
テーマが大きいのでまずフリートークとさせていただきます。先日9月4日の夜から5日の未明にかけて大変な集中豪雨がありました。4日の17時頃からぱらぱらと雨がきて家に帰っていったのですが、22時前くらいに警報がでました。環境防災課長と話し、同課長から「今から役場向かいます。」と聞き、役場へ出てきました。正直0時くらいに帰れるだろうという気持ちで行ったのですが、あんなになるとは思いませんでした。22時の予報は23時くらいになれば雲がどこかへ行くと。1時間くらい待機だなと思っていました。23時の予報では0時くらいまで雲が残るとなりました。0時予報では、6時くらいまでだと、しかも気象台の雲のレーダーでは雨雲がずっと続くということで、えらいことになったなと感じました。0時30分くらいに中上の三孤子川右岸の魚良さん付近が溢れました。それでその溢れそうになる前にレベル3の非難準備情報を出しましたが、30分くらいほどで左岸も溢れました。左岸側のほうが大変で、レベル5を出して家の中から出ないでください。家の中で上に逃げてください。と同報無線でも言い、車で1時間くらいずっと周りました。役場にも「何を言ってるのか雨の音で聞こえない。」と電話がかかり、「ともかく上に逃げてくれ。」という話をしたら、ある人が「うち平屋で上がないんだけどどこに逃げたらいいんだ。」という話がきました。場所はわかっているんで、その家は少し高くなっているのでそのままでいいと話をしに1時くらいに職員2人が行きました。ところが、そのお宅はよかったのですがお宅の下が腰くらいまであって職員がずぶぬれになって帰ってきました。そんなことでずっとどうなるのかなと思っていました。たぶん何十年ぶりかに三孤子川が越水し、中上で20件、穴太で10件くらいあわせて30数件床下床上浸水がありました。実は、土曜日に社会福祉協議会に大阪府枚方市からボランティアがきまして、中上を片付ける手伝いをボランティア6人に協力してもらったと自治会長から報告をいただきました。この報告書には五和会の会長さんが一生懸命働いてる写真も入っていますが中上は迅速に片付けていただいて、みんなで協力しあう、団結力がある、と思いました。皆さんのおかげで、残土・ごみはほとんど撤去されています。雨が6時間で400ミリメートルを超えたらしいんですが、計算すると1時間で70ミリメートルの雨が6時間続いたということになります。他の所なら大災害になっています。東員町はそれだけ災害に強い町ということを再確認させていただきました。なにより良かったことは人的被害が皆無であったということです。これからは本当に皆さんも気をつけて生活していただきたいなと思っております。こないだの災害については、今2億円弱の予算をつけまして、60箇所全てを復旧させていただきます。これも迅速に対応しなければいけないということで町の予算をつけました。今から災害申請を国に向けてします。どのくらい補助金がつくかはわかりませんが、ともかく迅速にやらさせていただきますので、皆さんも何かお気づきのことがあれば教えていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
9月から東員町で試し版も含めて、新聞を発行したいという会社があります。どんな新聞かといいますと、「グッドニュース新聞」。良い話しか掲載しないといった新聞を発行します。東員町は全戸配布しますが、あとはインターネット掲載にする予定です。記者は現在も募集をしていまして、予定では全国で5000人の記者を募集しています。まだ110~120人くらいですので皆さんもよろしくお願いします。例えば、どんなニュースかといいますと、1番身近なところからご紹介させていただくとノリタケカンパニー元社長で筑紫在住の種村均さんのお話です。東員町では松の会の会長をお願いしている人なんですが、その方の20年くらい前の話になります。ノリタケで課長をしていた時、バブルがはじけてリストラをすることになりました。たくさんの方々に勧奨退職をしてもらったんですが、どうしても家庭の事情で残らなければならないという方がいて、その方たちには職場を少し変わってもらいました。そのうちの一人が種村さんの隣の総務課付けで任用されたそうです。元々は工場で働いていた方が総務課の雑務係になられ、しょっちゅうたわいもない会話をしていたそうなんですが、ある日の朝その人が出勤されたら、もう凄い怪我をしていたそうです。「なぜそんな怪我をしたのか」と尋ねると、「昨日少し残業があり、遅くなっていたので急いでいて自転車で転倒した」と答えたそうです。その方は会社から電車に乗って、最寄り駅から自転車で通っていたそうです。「なぜそんなに急いで帰らなければいけないのか」というと、実は奥さんが10数年寝たきり状態です。子供たちは家を出て行っているので、妻の世話や晩ご飯を作らなければいけないので急いで帰ったところ、暗かったこともありこけてしまいました。色々話をしていると10数年ずっと介護をしながら、仕事をしており、そういう事情で会社に残らなければならなかったそうです。種村さんは隣の課でしたが、色々と相談にのっていたそうです。それからしばらくして、その方から種村さんに相談がありました。相談内容は、息子が結婚をするから同居したい。というものだったそうです。その方は、「別々に住んだほうがいいし、奥さんが大変になるから止めておけ」と強く言ったそうなんですが、息子がどうしてもときかなかったそうなんです。その理由は、自分のお母さんだから、自分もお父さんのように介護してあげたい。ということだったそうです。「奥さんはいいのか」と尋ねると、「あなたのお母さんは私にとってもお母さんだから」といったそうです。最終的には一緒に住むことになったそうですが、種村さん曰く、「息子さんはお父さんの背中をずっと見てきた。そのお父さんは介護を凄く楽しみながらしていたことを悟ったのだろう」とおっしゃっていました。その方が定年退職されて、しばらく経ってから偶然会ったらしいんですが、とても良い笑顔をされていたそうです。今は孫も含めて家族5人で幸せに暮らしており、種村さんは凄く羨ましい気持ちになったそうです。その当時種村さんはもうすでに社長に近い地位にいたと思うんですが、会社的にも社会的にも凄い高い地位にあります。だけど人生の勝者は自分ではなくこの人だなと強く思った、と話してくれました。種村さん自身はそこまで出来ない、とも語ってくれました。その方は生活に不満を持っていない。そこが凄いところだなと思います。人生はどうなるかわかりません。その状況になったときにどう考えるかだと思うんです。嫌だな、この生活から逃げたいな、と思ったときに受け入れて、そのなかで楽しみを見つけることで人の幸福は変わってくると思います、というようなエピソードです。これがグッドニュース新聞です。
続いて、非常に長生きされて活躍されている方のお話をします。お一人は、笹本恒子さんという方なんですが、この方は2014年に100歳になられた報道カメラマンです。今年で105歳の現役カメラマンです。若い頃にカメラマンになって、結婚し出産して休んでいましたが、ご主人が70歳を前に亡くなられて、もう一度カメラマンをすると決めたそうです。この方が心情としていることは、必ず背筋をピンと伸ばすということで、なぜかというと、人に見られたときに背筋が曲がっていると老けてみえるそうです。だから背筋を伸ばして颯爽と歩くことを心がけているそうです。10歳くらい若くみえるそうなので是非試してもらえるといいなと思います。また疲れたとかえらいとか私たちもよく言うんですが、絶対に言わない。禁句だそうです。それからこの方は香水が好きだそうで、100歳にして身だしなみはきちんとするんだそうです。必ず人前に出るときは身だしなみをきちんと整えます。好きな香水をつけて、いつも持ち歩いているそうです。人に若く見られたいんじゃなくて、不快にしたくないという気持ちでいるそうです。100歳を過ぎてもまだまだ現役で頑張る今年105歳の方の話です。是非みなさんもいつまでも若く、プロとか職業とかは別にして何か自分で打ち込めるものを持っている、集中できるものがあるということが若さの秘訣かなと思います。それからもう一人、新しい壱万円札の肖像画、渋沢栄一さんです。日本経済の父と言われています。この資本主義の日本経済の基を作り、いくつかの会社を立ち上げたり、関わった凄い方です。その渋沢栄一さんにお孫さんが一人いて、今年98歳の鮫島純子さんです。この方は、98歳ですが、全国を講演してまわっています。鮫島さんに来て欲しいというところは結構多いそうです。例えば1時間の講演すると主催者が椅子を用意し、そこへ座ってお話をしてください。となりますが、鮫島さんは絶対に座らないらしいんです。1時間立ったままお話をされるそうです。この鮫島さんは日本で1番最初にオレオレ詐欺にかかった人だそうで、凄い財産をお持ちの方なんですが、金融財産全部持っていかれたそうです。後に警察署へ行って「持っていてはいけない財産を私は持っていたんですね」と話したそうです。警察はお金を取られたことが嘘なんじゃないかと思ったそうです。ある講演で舞台にあがったそのときに司会の方が椅子を持ってきてくれたそうですが、鮫島さんは「ありがとう」といい、立ったままお話をされたそうです。1時間後講演を終了し、司会者の方に、「あなたの好意を無にしてごめんなさい」といわれました。その方のお話の中にはいつも「全てに感謝」という言葉が入ってくるそうです。だからオレオレ詐欺の方にも感謝だそうです。だから話に説得力があるんだと思います。とても90代には見えません。この方を一度東員町へ呼びたいと思っているんですが、忙しい方なので呼べるかわかりませんが講演してもらうとありがたいなと思っています。今年100歳以上の方は東員町では16人くらいみえるんですが、全員女性の方です。
もう一人だけ紹介すると、この方は昭和5年生まれの方で私のお袋と同い年なんですが、今年88歳です。この方は上中別府(カミナカベップ)チエさんという方なのですが、戦後の混乱で学校へ行けず、結婚し出産してご主人が亡くなられてからもう一度勉強したいと定時制の中学から定時制高校へ80歳を過ぎてから通われた方なんです。そこで野球部に入部しました。担任の先生が野球部の顧問やったこともあり、ドラフト1位で野球部へ入れたといっていました。なぜかというと、当時の定時制高校は先生の言うことは聞かない生徒が多かったのですが、チエさんの言うことは何でも聞くんです。だからチエさんを野球部に入れたらなんとか野球部はまとまるだろうということで入れたらしいんです。チエさんの任務は玉拾いとグランド整備だそうです。後は一人ひとりに声をかけることだそうです。実はチエさんは、たった一度だけ公式戦に出場したそうなんですが、11-1で勝ったそうです。その9回で守備につき、ボールは飛んでこなかったけれど、チエさんは「100歳まで生きるつもりなのにこの公式戦のせいで寿命が5歳縮まってしまった。」といったそうです。やはり女性は強いと思います。何かに打ち込んで一生懸命やる、そして女性は気遣いが出来ます。そういうところに男性は惹かれる、惚れるということなんですが、健康で長生きしていくにはどうすれば良いかということを我々は考えていかなければいけないと思っています。東員町は男性も女性も平均寿命は80歳を越えており、三重県下でも健康長寿の町となっています。そのことで三重大学と提携をして研究しています。成果が出たらまた皆さんにお知らせします。
最後に1つのコツみたいなこととして、東京工業大学の名誉教授森先生という三重県出身の方が提唱している非真面目のススメです。不真面目ではなく、非真面目です。例えば、テストの珍解答という本がありますが、これは試験で学生が実際に書いた解答が載っている本で、思わず先生が笑ってしまった解答です。この珍解答では、自給□□と書いてある問題に自給自足ではなく、自給千円と書いてあったというような本です。森先生が「電線にとまっている鳥はなぜ落ちないのか」と東工大の学生に問うと、理論上で重さやら比重やらの解答がたくさんあったそうですが、森先生が気に入った解答は、「鳥は落ちても良いと思っている。なぜなら飛べるから」こういう柔らかな発想をすることで頭も柔らかくなり、健康で長生きできるのかなと思います。堅いことばかり考えず、柔軟に生きてみても良いんじゃないかと先生はおっしゃっていました。我々もメリハリをつけて、きちんと考えなければいけないところは考えて、時には町民の皆さんと柔らかい話もしつつ、より良い東員町を作っていければと思っています。
質疑応答
男性1
新地域支援事業があると聞きましたが、東員町ではこのような事業はありますか。
長寿福祉課長
新地域支援事業ついてはまだ情報を掴んでおりません。現在の介護保険制度の中で、介護が必要になったときに使っていただくものとは別に地域支援事業というものがあります。これはいわゆる高齢の方たちの日常の生活を支えていくための事業です。例えば、介護予防事業。色々住民主体の介護予防の仕組みを作ったり、包括支援センターも高齢者の相談業務を行う地域支援事業です。そのほか、認知症の施策や在宅医療の制度などを介護保険の中で介護サービスとは別に地域支援事業として、それぞれの市町に応じた取り組みを行っています。今後色々な制度改正で新たな取り組みも出てくると思いますので、そのタイミングで新聞に出ていたかもしれませんが、地域支援事業は継続的に取り組んでいます。
男性2
私たち高齢者は大体80歳を過ぎると免許返納します。まずご主人が返納し、奥さんが軽自動車に乗ったとしても、奥さんも80歳を越えると子供から免許返納しろといわれます。夫婦2人で生活し、奥さんがまだ運転できる場合はいいんですが、両方免許返納すると移動手段がありません。高齢者の移動のサポートをどういう風なシステムにしていくのかについて重点的に取り組んでいただきたいです。もう1つは、リニアが名古屋まで来ますが、三重県の北勢地区は東員町も含めて、通学通勤圏内になってしまうわけなんですね。その後、大阪万博があってリニアが大阪まで延びると大阪も通勤圏になります。そういうところから東員町へ人を呼ぶことは不可能ではないと私は思っています。交通が発達すれば移動手段が変わってくるので、第6次総合計画にもこのことを組み込んでいただきたいです。
町長
まず免許返納について、これは今度の総合計画でも考えていかなければ思っています。例えば、オレンジバスのフリーパスを配布するということも考えていかなければならないと思っています。ただそれだけではカバーできないと思っていますので、別の交通手段も考えていかなければと思っています。
もうひとつリニアの件についてですが、リニア開通で環境は変わります。今年の新名神の開通でもずいぶん環境はかわりました。ただ、私は地域に人を呼びこむにはいくら便利になったからといっても来ない人は来ないと思っています。人を呼ぶ要因は、地域に魅力をつくることです。そうしないと絶対に人は来てくれません。だから今東員町がしなければならないことは東員町に魅力をつくることです。東員町に来たいと思える町をつくることが大切だと私は考えています。昨年のふれあいトークでは大豆の話をしたと思うんですが、今、大豆プロジェクトが進んでいます。農林水産省まで足を運んで、工場やカフェ・レストラン等を含めて農業的な開発をしていき、東員町のオンリーワンを作っていこうということを考えています。こういったことを発信していくことで東員町がどんなところかを知ってもらえると思っています。今回の災害で東員町は全国に知られましたが、災害であまり有名になってもというとこもあります。やはり施策や魅力で東員町を全国区にしていけたらと思っています。それによって東員町に足を運んでくれるだろうと思っています。行政だけで全てできるわけではありませんので、町民の皆さんが一緒になって魅力作りをやっていただけると活性化につながりますのでご協力をお願いします。
備考
(補足)記録は要約してあります



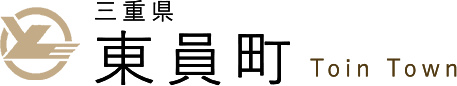

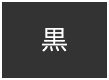
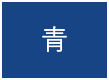
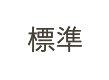
更新日:2024年03月29日