後期高齢者医療制度(届出・申請など)について
後期高齢者医療制度
制度の概要
75歳以上の全ての方と、65歳から74歳までで一定の障がいがあり認定を受けた方は、この制度のもとで医療を受けることができます。
なお、制度の運営は、三重県全市町が加入する「三重県後期高齢者医療広域連合」が行います。
対象者
75歳以上の全ての方と、65歳から74歳までで一定の障がいがあり、認定を受けた方(制度に加入するには申請が必要です)
資格を取得する日
- 75歳の誕生日から
- 65歳から74歳で一定の障がいのある方は申請し、広域連合の認定を受けた日から
被保険者証
被保険者証は一人一枚ずつ交付します。
医療機関を受診する際は、『後期高齢者医療被保険者証』を医療機関窓口に提示してください。
自己負担割合
| 所得区分 | 負担割合 | 所得基準 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3. | 3割 | 住民税課税所得(各種控除後)が年額690万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯に属する被保険者 |
| 現役並み所得者2. | 3割 | 住民税課税所得(各種控除後)が年額380万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯に属する被保険者((注釈)1参照) |
| 現役並み所得者1. | 3割 | 住民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の被保険者及びその方と同じ世帯に属する被保険者((注釈)1参照) |
| 一般2. | 2割((注釈)2参照) | 住民税課税世帯で、次の1、2の両方に該当する世帯の被保険者。(現役並みの所得者を除く。)
|
| 一般1. | 1割 | 住民税課税世帯で、現役並所得3.~1.、一般2.のいずれにも該当しない被保険者 |
| 低所得2. | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、低所得1.以外の被保険者 |
| 低所得1. | 1割 | 世帯全員が住民税非課税で、すべての世帯員の各所得が0円となる被保険者。ただし、公的年金等控除額は80万円として計算。 |
- (注釈)1.ただし、上記所得のもとになる収入額が次の条件に当てはまるときは、申請のあった日の翌月より所得区分が『一般1.(1割負担)』となります。
基準収入額適用申請
同一世帯に被保険者が1人の場合
被保険者の年間収入額が383万円未満
ただし、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合は、被保険者及びそれらの
方全員の年間収入額の合計が520万円未満
同一世帯に被保険者が2人以上の場合
被保険者全員の年間収入額が520万円未満
- (注釈)2.なお、窓口負担割合が2割となる方については、3年間(令和7年9月30日まで)、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置があります。(入院の医療費は対象外)
こんなときは手続きを
次のような場合には、手続きが必要です。手続きは保険年金課で受け付けています。
加入の手続き
- 東員町に転入したとき…負担区分等証明書((注釈)1参照)、本人確認書類
- 生活保護を受給しなくなったとき…生活保護廃止通知書、本人確認書類
- 障がい認定を受けるとき…障がいを証明する書類((注釈)2参照)、本人確認書類
- (注釈)1 県外から転入したときは前住所地で発行された「負担区分等証明書」を転入手続きの際に提出してください。
- (注釈)2 65歳から74歳で一定の障がいがある方に限られます。
加入手続きの際に、「預金通帳」、「口座届出の印かん」を持参いただければ『口座振替』の手続きも行うことができます。
脱退の手続き
-
東員町から転出するとき…保険証、本人確認書類
県外へ転出するときは、申請いただいたうえで「負担区分等証明書」をお渡ししますので、転入される市区町村の窓口へご提出ください。 - 生活保護を受給するようになったとき…保険証、生活保護開始通知書、本人確認書類
- 障がい認定を撤回するとき…保険証((注釈)1参照)、本人確認書類
- 亡くなられたとき…保険証、喪主の方の預金通帳(葬祭費支給)、本人確認書類
(注釈)1 65歳から74歳で一定の障がいがある方に限られます。
その他《変更等》の場合
- 町内で転居したとき…保険証、本人確認書類
- 記載内容(氏名等)に変更があるとき…保険証、本人確認書類
- 保険証等を紛失、破損したとき…保険証(破損の場合)、本人確認書類
後期高齢者医療の給付
後期高齢者医療制度で受けられる医療の給付は以下のものがあります。
医療機関では、被保険者証の提示によって医療の給付の受給資格を確認しますので、必ず医療機関窓口で被保険者証を提示してください。
療養の給付
療養の(病気やケガをしたとき)について、医療機関の窓口で保険証を提示して次の給付を受けることができます。
- 診療
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院等
なお、医療機関での自己負担割合は、所得により『1割』または『3割』となります。
(負担割合の所得基準については自己負担割合の表を参照してください。)
入院時食事療養費
入院したときの食費は下表のとおり(1日3食まで)が自己負担額となります。
低所得者(住民税非課税世帯)の方は、申請することにより入院したときの食費が減額されます。
| 所得区分 | 1食あたりの食費 |
|---|---|
| 現役並み所得者(3.・2.・1.)・一般 | 510円((注釈)1参照) |
| 低所得2.(過去12か月の入院日数が90日以内) | 240円 |
| 低所得2.(過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当)((注釈)2参照)) | 190円 |
| 低所得1. | 110円 |
- (注釈)1 指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中などのか方は300円の場合もあります。
- (注釈)2 低所得2.に該当し、過去12か月の入院日数が90日を超える場合(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)は、病院の請求書・領収書など入院日数のわかる書類を添えて保険年金課へ申請してください。なお、原則として長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
- 所得区分の所得基準については自己負担割合の表を参照してください。
- あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
入院時生活療養費
療養病床に入院したときは、食費と居住費に係る費用のうち下表の額が自己負担額となります。
低所得者(住民税非課税世帯)の方は申請することにより、生活療養費が減額されます。
【病状の程度や治療内容により、負担額〔医療区分1.・2.・3.〕が異なります。】
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1食あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(3.・2.・1.) ・ 一般 | 510円 ((注釈)1参照) | 370円 |
| 低所得2. | 240円 | 370円 |
| 低所得1. | 140円 | 370円 |
| 低所得1.(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 ((注釈)3参照) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者(3.・2.・1.)・一般 | 510円 ((注釈)1及び2参照) |
370円 |
| 低所得2.(過去12か月の入院日数が90日以内) | 240円 | 370円 |
| 低所得2.(過去12か月の入院日数が90日超(長期入院該当) ((注釈)4参照)) | 190円 | 370円 |
| 低所得1. | 110円 | 370円 |
| 低所得1.(老齢福祉年金受給者) | 110円 | 0円 |
-
(注釈)1保険医療機関の施設基準等により、470円の場合もあります。
-
(注釈)2 指定難病患者の方、一定期間精神病床に入院中などのか方は300円の場合もあります。
-
(注釈)3 指定難病患者の方は0円です。
-
(注釈)4 低所得2.に該当し、過去12か月の入院日数が90日を超える場合(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)は、病院の請求書・領収書など入院日数のわかる書類を添えて保険年金課へ申請してください。なお、原則として長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
-
所得区分の所得基準については自己負担割合の表を参照してください。
-
あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受ける必要があります。
療養費
次のような場合で医療費の全額を支払ったときに、申請することにより支払った費用の一部を支給します。
- 急病などで被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 医師の指示で、コルセットなどの補装具を作成したとき
- 医師が必要と認めた、はり、灸、マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき
- 海外渡航中に診療を受けたとき
- 手術などで輸血に用いた生血代
高額療養費
1か月の医療費が高額になったときは、下表の自己負担限度額を超えた分が対象となります。限度額を超える窓口負担をした方へは、初回のみ申請が必要となり、広域連合から申請書を送付し、その申請に基づき支給します。以後、生じた高額療養費は先に登録した口座に振り込まれます。
- (補足)同一医療機関等の窓口での支払いは、月ごとに自己負担限度額までとなります。
- (補足)現役並み所得者2.・1.の方は『限度額適用認定証』、低所得2.・1.の方は『限度額適用・標準負担額減額認定証』の交付を受け、医療機関などの窓口に提示が必要です。
- (補足)差額ベッド代など保険診療外のものや入院時食事代などは対象になりません。
| 所得区分 | 外来 (個人ごとの限度額) |
世帯単位 (入院と外来があった場合の限度額) |
4回目以降((注釈)1参照) |
|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者3. |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| 現役並み 所得者2. |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| 現役並み 所得者1. |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 一般 | 18,000円((注釈)2参照) | 57,600円 | 44,400円 |
| 低所得2. | 8,000円 | 24,600円 | なし |
| 低所得1. | 8,000円 | 15,000円 | なし |
- (注釈)1 過去12か月以内に世帯で3回以上の高額療養費が支給されている場合における4回目からの限度額です。
- (注釈)2 1年間(8月~翌年7月)の個人ごとの外来の自己負担額の合計額に、年間 144,000円の上限があります。
なお、所得区分の基準については自己負担割合の表を参照してください。
特定疾病の治療を受けるとき
厚生労働大臣が指定する特定疾病については『後期高齢者医療特定疾病療養受療証』を医療機関の窓口に提示することにより、毎月の自己負担額が10,000円までとなります。
特定疾病の治療を受けるには、事前に申請が必要となります。
申請に必要なもの…保険証、特定疾病であることがわかるもの、本人確認書類
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 先天性血液凝固因子障害(血友病)の一部
- 人口透析が必要な慢性腎不全
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
高額介護合算医療費
被保険者と同じ世帯内で、後期高齢者医療制度と介護保険の両方から給付を受けることにより、1年間(8月から翌年7月分)の自己負担額が高額になったときは、対象者に広域連合から申請書を送付します。その申請に基づき後日、自己負担限度額を超えた分を支給します。
- (補足)自己負担額は、高額療養費が支給される場合には、当該支給額が控除された額になります。
- (補足)後期高齢者医療制度の被保険者以外の方の自己負担額は合算されません。
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額) |
|---|---|
| 現役並み所得者3. | 212万円 |
| 現役並み所得者2. | 141万円 |
| 現役並み所得者1. | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得2. | 31万円 |
| 低所得1. | 19万円 |
限度額を超える額が500円以下の場合は、支給対象となりません。
第三者行為の届け出
交通事故や傷害事件など、第三者の行為によってケガをして治療を受ける場合は、原則として加害者が医療費を負担すべきものですが、保険証を使用するときは、必ず保険年金課へ届け出てください。
葬祭費
被保険者が死亡したとき、葬祭をおこなった方(喪主)に対し、申請により葬祭費を支給します。
支給額 50,000円
後期高齢者医療 保険料
後期高齢者医療制度では、全ての被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し賦課します。
保険料の算定方法・納め方など
次のリンクをクリックしてご確認ください。
災害にあった場合
災害にあった場合や生活困窮により、保険料の納付が著しく困難な場合などは、一定の基準に基づき申請による保険料の減免措置があります。
Q&A(質疑応答)
問1 どのような制度ですか?
老人保健制度で医療の給付を受けていた方は、国民健康保険または被用者保険などの医療保険に加入していましたが、「後期高齢者医療制度」では現在加入している医療保険(社保、共済、国保等)から脱退し、「後期高齢者医療制度」の被保険者となります。
問2 制度の運営主体は?
老人保健制度では市町村が運営主体となっていましたが、後期高齢者医療制度では三重県の全市町が加入する「三重県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、資格の認定のほか、保険料の決定や各種給付の審査・支払などを行います。
問3 対象者は?
75歳以上のすべての方と、65歳から74歳の一定の障がいのある方で当該制度への加入を選択し、広域連合の認定を受けた方が対象です。
- 75歳の誕生日から被保険者となります。
- 65歳から74歳の一定の障がいのある方は、広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
問4 保険料はどうなるのでしょうか。
被保険者となる方それぞれに後期高齢者医療の保険料を負担していただくことになります。
保険料額は、各被保険者の前年の所得に応じて負担いただく「所得割額」と、被保険者全員に負担いただく「被保険者均等割額」との合計額となり、広域連合が保険料額を決定し、町が保険料の徴収を行います。
また、低所得の方や後期高齢者医療制度加入前に被用者保険(社保、共済等)の被扶養者であった方については、軽減制度が適用されます。なお、保険料額には、上限(限度額64万円)が設けられています。
問5 保険料はどうやって納めるのでしょうか。
年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引き(特別徴収)になります。ただし、介護保険料とあわせた保険料が年金額の1/2を超える方は納付書または口座振替により納めていただきます。
ただし、納付方法について「年金天引き(特別徴収)」と「口座振替」との選択が可能ですので、口座振替を希望されます方は役場窓口までお申し出ください。
問6 保険料の軽減措置について知りたいのですが。
低所得の方については、世帯の所得に応じて次の軽減措置が適用されます。
均等割額
7割・5割・2割
また、後期高齢者医療制度に加入される前日まで被用者保険(社保、共済等)の被扶養者であった方は、今まで保険料の負担がなかったことから、加入後当分の間、被保険者均等割額のみ資格取得から2年間を5割軽減した額を保険料として納めていただきます。なお、この期間中、所得割額は賦課されません。
問7 被保険者証はどうなるのでしょうか。
後期高齢者医療被保険者証(カード)を被保険者の方一人ひとりに発行します。
問8 自己負担はどうなるのでしょうか。
自己負担額はかかった費用の1割ですが、現役並の所得がある方は3割となります。
また、自己負担の限度額については老人保健制度と同様に月ごとの上限額が設定されます。
さらに、 医療機関で支払った額と介護保険の自己負担額の合算額について、年単位で上限を設けることにより、負担を軽減する制度(高額介護合算療養費制度)や、老人保健制度と同様の各種給付制度があります。
自己負担限度額の所得判定対象者は同じ世帯におられる 全被保険者が対象となります。
◇高額介護合算療養費とは…
医療費と介護サービス費の両方の負担が高額となり、家計の負担が重くなっている場合に、その負担を軽減するため新たに設けられた制度であり、内容は次のとおりです。
1年間(算定期間 8月1日~翌年7月31日)に支払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合計した額が、自己負担限度額(年額)を超えた場合、申請することにより超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。
詳しくは次のリンクをクリックしてご覧ください。



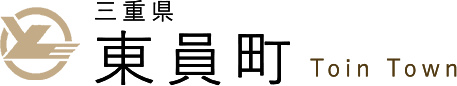

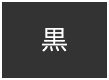
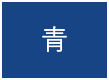
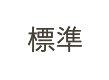
更新日:2025年05月16日