帯状疱疹ワクチン定期接種について
帯状疱疹ワクチン定期接種について
令和7年4月から、65歳の人などを対象に帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まりました。
(補足)50歳以上65歳未満の人を対象とした費用の一部助成については、こちら(任意接種のページ)をご確認ください。
帯状疱疹とは
水ぶくれを伴う赤い発疹がピリピリとした痛みとともに、体の左右どちらかの一部に帯状に現れる皮膚の疾患です。子どもの時にかかった水ぼうそうウイルスが体の中で長期間潜伏し、数十年たって加齢や過労、ストレス等により免疫力が低下した際に、帯状疱疹として発症します。
50歳以上になると発症のリスクが高まり、80歳までに約3人に1人が発症すると言われています。また、子どもの症状に比べて重いことが多く、治ってからも痛みが続く後遺症に悩まされる場合もあります。
定期接種対象者
- 年度内に65歳になる人
- 接種当日に60歳以上65歳未満の人であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
(注意)既に帯状疱疹ワクチンを接種したことがある人は、原則対象外となります。
経過措置
経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下の人も対象となります。
- 65歳を超える人については、5歳年齢ごと(当該年度内に70、75、80、85、90、95、100歳になる人)
- 101歳以上の人については、定期接種開始初年度に限り全員
|
|
70歳 |
75歳 |
80歳 |
85歳 |
90歳 |
95歳 |
100歳 |
101歳~ |
|
2025 (令和7) 年度 |
1955年 (昭和30年) |
1950年 (昭和25年) |
1945年 (昭和20年) |
1940年 (昭和15年) |
1935年 (昭和10年) |
1930年 (昭和5年) |
1925年 (大正14年) |
1924年 (大正13年) 以前 |
|
2026 (令和8) 年度 |
1956年 (昭和31年) |
1951年 (昭和26年) |
1946年 (昭和21年) |
1941年 (昭和16年) |
1936年 (昭和11年) |
1931年 (昭和6年) |
1926年 (大正15年・ 昭和元年) |
経過措置終了 |
|
2027 (令和9) 年度 |
1957年 (昭和32年) |
1952年 (昭和27年) |
1947年 (昭和22年) |
1942年 (昭和17年) |
1937年 (昭和12年) |
1932年 (昭和7年) |
1927年 (昭和2年) |
|
|
2028 (令和10) 年度 |
1958年 (昭和33年) |
1953年 (昭和28年) |
1948年 (昭和23年) |
1943年 (昭和18年) |
1938年 (昭和13年) |
1933年 (昭和8年) |
1928年 (昭和3年) |
|
|
2029 (令和11) 年度 |
1959年 (昭和34年) |
1954年 (昭和29年) |
1949年 (昭和24年) |
1944年 (昭和19年) |
1939年 (昭和14年) |
1934年 (昭和9年) |
1929年 (昭和4年) |
|
|
2030 (令和12) 年度 |
経過措置終了 |
|||||||
(補足)当該「年度生まれ」の人が対象
(例)1955(昭和30)年度生まれの人=生年月日が「1955年4月2日~1956年4月1日」の人
接種期間
令和7年4月1日~令和8年3月31日
(注意)この期間内に接種できなかった場合、その後の接種は助成対象外となります。
対象ワクチン及び接種回数、自己負担金
|
|
生ワクチン(ビケン) |
不活化ワクチン(シングリックス) |
|
接種回数 |
1回 |
2回(2か月間隔) |
|
自己負担金 |
2,500円 |
6,000円/回 |
(注意)助成を受けられるのはどちらか一方のみで、生涯に一度きりです。
ワクチンについて
|
|
生ワクチン(ビケン) |
不活化ワクチン(シングリックス) |
|
接種方法 |
皮下注射 |
筋肉内注射 |
|
予防効果 |
50~60%程度 |
90%程度 |
|
副反応 |
発赤、そう痒感、熱感、疼痛、硬結など |
疼痛、発赤、腫脹、筋肉痛、疲労、頭痛、悪寒、発熱、胃腸症状など |
出典:ワクチン添付文書、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料
(補足)生ワクチンとは毒性や病原性を低下させた(生きている)細菌・ウイルスを利用して作ったワクチンのこと。
(補足)不活化ワクチンとは毒性や感染力を失った(生きていない)細菌・ウイルスを利用して作ったワクチンのこと。
接種医療機関
県内の医療機関(事前に医療機関へ接種日等をご相談ください。)
その他
- 定期接種の対象者がすでに一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。(1回目を任意接種として取り扱い、2回目のみを定期接種として取り扱う。)
- 帯状疱疹ワクチンの交互接種(2種類の異なるワクチンを組み合わせて接種すること)はできません。
任意接種助成事業について
令和5年10月1日より実施している帯状疱疹ワクチン任意予防接種費用の一部助成は、令和7年4月1日より65歳以上の人への助成を廃止し、対象年齢を50歳から64歳に変更して実施をします。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種を受けたことにより健康被害が生じたと認められた場合、予防接種法に基づき、救済が受けられます。
この記事に関するお問い合わせ先
東員町 健康長寿課
電話番号:0594-86-2823
ファックス番号:0594-86-2851
お問い合わせフォーム



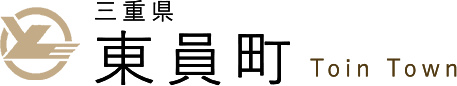

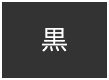
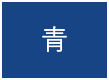
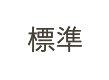
更新日:2025年04月01日