平成27年度 町政懇談会の開催状況
平成27年度 自治会別町政懇談会
10月3日から11月15日の間、23自治会にお伺いし、町民の皆さんからご意見をいただく町政懇談会を実施しました。
672人の皆さんにご出席いただき、様々なご意見をもとに、懇談をさせていただくことができ、ありがとうございました。
各自治会での懇談会会議録(要旨)は、順次公表していきます。
町政懇談会資料
町政懇談会次第
- 開会
- あいさつ
- 人口の減少と今後の推移 政策課
- 財政面から見た今後の東員町 財政課
- マイナンバーのお知らせ 財政課
- これからのまちづくり 町長
- 皆さんとの懇談
- 閉会
政策課 「人口の減少と今後の推移」要旨
日本の人口は2008年をピークに減少傾向で、2060年には8,700万人程度と推計されています。東員町でも、1999年をピークに、2040年には2万人程度と推計されています。
東員町の人口比率の推移と推計(1960年~2040年)を「年齢3区分別人口」で見てみると、年少人口(0歳~14歳)は1990年にピークを、生産年齢人口(15歳~64歳)は2000年にピークを向え、以降は減少に向っています。老年人口(65歳~)は、2010年には21%近くになり、2040年には、38%になると推計されています。
また、出生・死亡数、転入・転出数においても、自然減(出生<死亡数)、社会減(転入<転出)の傾向が続いています。
人口減少社会が影響し…「生活環境など」「子育て、教育」「医療、福祉」「産業」などに対策が必要と言われています。
しかし人口減少社会の良いところもあり…「拡大・成長路線の発想だけではなく、本当の意味の豊かさを追求」などと言われています。
財政課 「財政面から見た今後の東員町」要旨
町の財政について、先ほどの人口推移と重ね合わせて考察します。
歳入・歳出、それぞれ人口の変動に影響を受けやすい科目を抜き出してみると、歳入では、主な納税者である20歳~64歳の人口の減少に伴い個人住民税は減額
歳出では、老年人口(64歳~)の増加に伴い社会保障関係費が増加し、10年後からは横ばい傾向が続いていきます。
本町の財政状況は年々厳しくなりますし、公共施設の維持管理の費用も増加してきます。公共施設の維持管理計画の策定や、歳出の更なる見直しを行い、効率的な行政運営を持続的に進めていく必要があります。
財政課「マイナンバーのお知らせ」 要旨
個人番号通知カードが、10月5日現在の住民票をもとに、世帯毎に簡易書留で郵送されます。
現在の情報として、本町では11月中旬からの配達と聞いています。個人番号通知カード(紙製)には、みなさんのマイナンバー(個人番号)が記載されています。所定の手続きを行っていただきますと、個人番号カード(プラスチック製)をお持ちいただくことになります。
個人番号カードを使って、インターネットでの確定申告や、東員町では住民票や納税証明などの発行をコンビニでも出来るよう進めてまいりますので、ご活用いただけることになります。趣旨を御理解のうえ、個人番号カードへの申請にご協力いただきたいと思います。重要な番号となりますので、大切に保管いただくようお願いいたします。
町長「これからのまちづくり」 要旨
元岩手県知事の増田寛也さんが座長を務める民間研究機関の日本創生会議が、2014年5月公表したいわゆる「増田レポート」は「2040年には40%の地方の自治体が消滅する可能性を持っている」という衝撃的なものでした。実際はそうはならないと思いますが。
そんな中で、今都会の若い人が地方にたくさん移住して、移住先の人口、子どもの数も増えている現象があります。このような状況を調査することで、我々がすべき方向性が見えてくると思います。
先月、富山県上市町と北海道弟子屈町に視察に行ってきました。いずれも人口減少が進み、観光客も減っている状況ですが、自分たちがこれから生き残ることを真剣に考えています。
具体的には、町内で採れた農産物等を、いかに付加価値をつけて売り出すか考えています。また、町内にある歴史・自然・文化で売り出せるものがあるかどうかを探し出し、観光客を誘致し、お金を落としてもらう仕組みを作っています。
例えば、弟子屈町では、夜の摩周湖に観光客を連れて行き、一人3000円で星を見せ、プロのガイドが説明をする。一人3000円ですが非常に流行っているとのことです。ガイドの養成も行っているそうです。
また、富山県上市町では、1万円のランチが人気だそうです。食材にも徹底的にこだわり、食べるには予約が必要だそうです。非常に高価なランチが人気な理由は、人にはそれぞれ記念日があり、その記念日にあわせて、高級ランチを食べにくるそうです。 企業であれば、大切なお客さんとの食事に使われるそうです。予約制なので無駄がありません。
30,000円を売り上げるには、500円ランチであれば60食、1,000円ランチであれば30食の販売が必要ですが、10,000円ランチであればたった3食の販売で良いわけで、利益率も格段に高いとのことです。その店の食材は地元産の物しか使われず、地元の第1次産業も潤うこととなります。
大人も子どもも含め国民1人あたりが、1年間で飲食も含め「物を買う」ことに使うお金は、全国平均で110万円程度だそうです。このうち1%を、東員町の食材・店にこだわって使っていただくと、単純計算で2億5000万円のお金が町内で循環することになります。これは年収500万円の人、50人分の雇用にもつながることになります。
東員町に置き換えてみると、なかなか特産物が思いつきません。東員町には、歴史・文化・祭り等すばらしいものがたくさんありますが、それを利用してお金を稼ぐ仕組みが欠けていると思います。
今後、我々が目指すべきところは、そこだと思います。歳入アップに企業誘致と言われるかもしけませんが、町内にはまとまった大きな場所がありませんし、また規制がかかっている場合もあります。
そんな中で、何か考えないといけないということから、長深の耕作放棄地を、畑に戻し、昨年から試験的にぶどう・ブルーベリーの栽培を始めました。行政が直接農業を行うことの理由には農家が新しい分野を始めるには、自然に左右され、収穫が本当にできるのかという、大きなリスクが伴いなかなか前に進めないのが現状です。そのリスクを町が負うことにより、農家のリスク回避ができ、新たな分野への取り組みが始められます。ぶどう・ブルーベリーが東員町で収穫できることが軌道にのってきたら、町内の農家や企業にぶどう・ブルーベリー栽培を行ってもらい、加工品も含め、東員町の特産品にしていきたいと考えています。
また、隣の畑地では、農福連携就労として、民間企業が障がいのある方の就労として、サツマイモやゴマの栽培を行っています。これは、出来た作物をすべて買い取ってもらう契約を先に済ませたもので、出口を確保した状態で農業を行っています。障がいのある方も一生懸命就労していただき、月額100,000円以上の稼ぎがあるそうです。こういうことを拡大していくことにより、雇用も生まれ、新たな産業も生まれてくる。そんな挑戦をおこなっています。
三重県保健環境研究所のデータですばらしいものがあります。東員町の方の平均寿命は、男女とも、全国平均を上回ってますが、いま注目されている「健康寿命」についても、高い数値となっています。また、男性が女性の健康寿命を上回っており、県内でもトップクラス、東員町近隣の市町の中ではトップです。非常にすばらしいことです。これは、町民皆さんが、ボランティア、文化、スポーツにご活躍いただいており、生きがいを持って暮らしていただいているからこそだと思います。もう少し詳しい分析を三重大学とタイアップして、行っていきたいと考えています。
研修してきました町では、町民主体としたまちづくりの意思決定機関が組織されており、町民、商工会、農協、社会福祉協議会等、様々な組織も入り、町民主体であることがはっきりとわかる組織が立ち上げられています。東員町もそういう組織づくりをしていかないといけないと思っています。
いま空き家の調査を行っています。どこに何戸というだけでなく、所有者の方が今後どうしていくのか、売却されるのか、活用させてもらえるのかも含め調査しています。もう少しで調査結果が出てくると思います。若い人の古民家ブームにうまくのっかり、東員町も空き家を活用していくべきだと考えています。全国では、古民家のリフォーム・活用も含め、地域住民主体で活用を図っている組織もあります。
今後やるべきことはたくさんありますが、行政のやれることは非常に少ない。町民の方に主体となっていただき、また東員町には元気な高齢者の方々が多いですから、ぜひ高齢者の方にもがんばっていただき、お金を稼ぐ仕組みづくりをお願いしたいと思います。



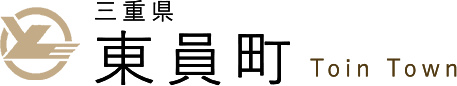

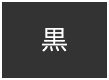
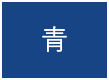
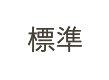
更新日:2024年03月29日